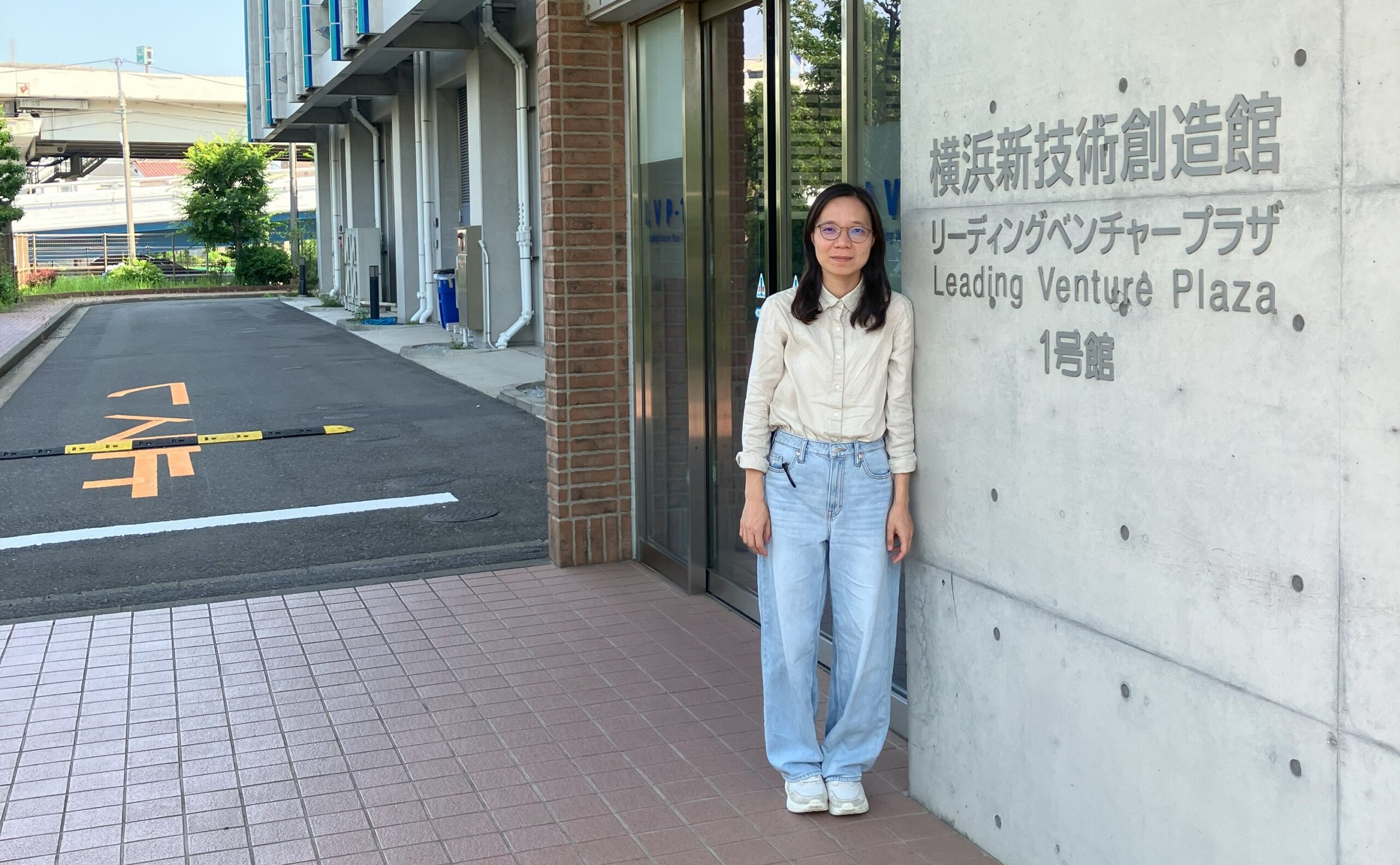【社員インタビュー】微生物から植物へ。アクプランタで見つけた「社会につながる研究」

2025年4月、ベトナム出身のQuyen Tran(クエン・トラン)がアクプランタの研究開発チームに加わりました。
クエンはベトナム出身ですが、日本での留学経験もあります。学士課程と修士課程では廃水処理について研究し、博士課程とポスドク課程では、東京科学大学で堆肥についての研究を行いました。このように、アカデミックの現場で多くの経験を積んできた彼女が、なぜ、スタートアップの「アクプランタ」を選んだのか。その理由と、これからの挑戦を聞きました。
本記事が、クエンの人となりや、アクプランタをさらに知っていただける機会となれば嬉しいです。
アクプランタとは?
社長の金が、理化学研究所の研究員時代に発見した研究成果をもとに、植物の乾燥・高温耐性を強化するバイオスティミュラント資材*1『Skeepon(スキーポン)シリーズ』を開発・販売している会社です。
プロフィール
ベトナム出身。東京科学大学で博士号を取得後、ベトナム国家大学の専任講師として同僚と環境学部を設立し、国内の環境問題解決に尽力。その間、イギリスの王立工学アカデミーの「イノベーション・リーダー育成プログラム」も修了した。2年後、日本に戻り、母校で5年間のポスドク研究員として従事した。研究は堆肥化に焦点を当て、有機廃棄物の持続可能な農業利用を目指し、食品廃棄物などにおける有用な微生物を特定。手法は、次世代シーケンスによる微生物動態の解析で、堆肥品質と土壌改良効果を植物試験で評価した。現在はアクプランタのR&Dチームに所属。
フィリピンのデ・ラ・サール大学での会議に出席
―――これまでの経歴をおしえてください。
私はベトナム出身で、学部では化学工学を学びました。修士課程はフィリピンで、その後、東京工業大学(現在の東京科学大学)で博士号を取得しました。研究テーマは、生ごみを微生物で分解し、肥料に変える「コンポスト」でした。博士課程修了後は、ベトナムの大学で講師を務めた後、日本に戻ってポスドクとして5年間、微生物とコンポストの応用研究に取り組みました。
―――微生物に関心を持ったきっかけは?
学部では化学が専門だったのですが、化学というのは「無生物」の世界なんですね。微生物は生きていて、働き方がとても柔軟です。たとえば、酸性のごみが多すぎると普通はコンポストが失敗します。でも、ある特定の微生物を入れると、その酸を中和して、きちんと発酵が進むんです。人間の手ではコントロールできないようなことを、微生物ができる。それを目の当たりにして、強く惹かれるようになりました。
―――ポスドク(博士研究員)では、どんな研究をしていたのですか?
コーヒー豆のかす、水産スラッジなど、いわゆる産業副産物をどうコンポスト化するかを研究していました。水産スラッジというのは、水産養殖の現場で魚の排泄物やエサの残り、水の汚れなどが混ざった、いわば「養殖場の底にたまる泥」です。窒素やリンといった栄養分が豊富に含まれているのですが、そのまま捨てると環境に悪影響を与えます。そのため、私たちはそれを微生物で処理し、発酵させ、そこから「クリーン窒素」と呼ばれるアンモニアガスを取り出す研究をしていました。
東京理科大学の研究室で、堆肥化プロセスのメカニズムを解明する実験を繰り返した
―――アクプランタの第一印象はどうでしたか。
出産を機に一度、研究現場からは離れたのですが、再び研究の世界に戻りたいと考えていました。そんなとき、「微生物」「農業」などのキーワードで求人を探したところ、アクプランタが目に留まりました。スキーポンという資材が植物の持つ力を引き出し、成長や耐性をサポートするという話を知り、「微生物と植物の接点をもっと学びたい」という自分の興味と重なりました。
面接では、自分が持っている化学・生物・微生物の基礎知識をもとに、植物研究に挑戦したいという気持ちを正直に伝えました。社長の金さんとも話が弾み、「一緒に働いてみよう」と言っていただきました。
―――アクプランタではどんな研究に取り組んでいますか?
植物が高温や乾燥といったストレスにどう反応するのかを、RNA(リボ核酸※遺伝情報の伝達やタンパク質合成に関与する重要な分子)レベルで調べています。
RNAは、今、その生物がどのように働いているかを示す指標です。DNAが「設計図」だとすると、RNAは「現在の活動記録」です。同じDNAを持つ双子でも、都会で暮らす人と田舎で暮らす人とでは、RNAの発現が変わります。それと同じで、スキーポン処理した植物がどんな遺伝子を活性化させているのかを知ることで、その効果をより深く理解できます。
以前はDNAをたくさん扱っていたので、DNAの抽出や解析には慣れていました。しかし、RNAは私にとって新しい分野なので、慣れるのに時間がかかっています。すごく興味深く、同僚から知識や技術を学べるのも嬉しいです。今は勉強中ですが、すでに自分である程度できるようになってきました。
アクプランタの研究室がある「横浜新技術創造館」の前にて
―――アクプランタの職場環境はいかがですか?
とても風通しがよく、自由に意見を出し合える環境です。企業で働くことはこれが初めてですが、アクプランタでは研究内容や結果に対して、すぐに、直接、フィードバックが得られる環境が整っています。専門が違うメンバーが集まっているので、自分とは違う角度からの視点が得られるのも面白いですし、みなさんとても親切で、必要な機材や実験材料などもすぐに手配してくれます。
それに何より、研究が「社会とつながっている」と実感できます。農家さんから直接いただいた「こういう課題がある」という声を出発点に、研究ができる。そして、その研究の成果がまた現場に返っていく。そんなサイクルの中で、自分の研究が役に立っていると感じられるのは、なかなか得られない喜びです。
―――今後の抱負を教えてください。
これまでの微生物やコンポストの知識を生かしながら、植物の生理や根の働き、土壌環境の改善など、新しい分野にも挑戦していきたいと思っています。アクプランタのように、研究と現場がつながっている環境で、社会に貢献できる科学を実践していきたいです。